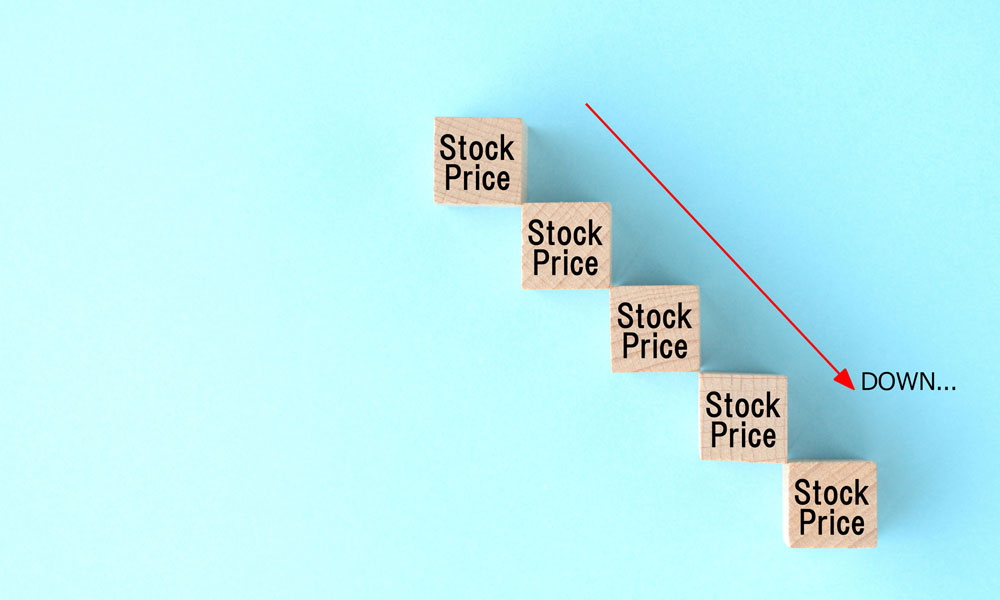評価損を計上することによる節税方法をご存知ですか?実際に資産を処分せず会社に残っていたとしても評価損として経費計上できる場合があります。今回の記事では棚卸資産の損金算入が認められる条件や、節税対策として行う場合の注意点について解説していきます 。
評価損による節税とは
節税方法には大きく分けて手元から資金が出ていく節税と、手元資金が出ていかない節税方法があります。今回ご紹介する評価損は「手元資金が出ていかない節税方法」に該当するもので、会社から資金も出て行きませんし、条件に該当すれば節税効果も大きなものとなります。
評価損とは
まず「評価損」とはどのようなものなのでしょうか。評価損とは会社が保有している在庫の価値が下がることで発生する損失のことを指します。 今までの価格で販売することが何かしらの理由で難しくなった場合には、今抱えている在庫を販売した時に得られる利益も減少するということになっています。この利益の減少分を会計上「評価損」として計上することで、会計を実際の状況により近づけることができます。
評価損が節税になる仕組み
商品の評価損は損益計算書において「売上原価」または 臨時の事象、金額が多額である場合には「特別損失」として計上します。
売上原価、特別損失いずれに計上するとしても、評価損を計上するとその分会社としては経費がその分増えますので、支払う法人税等の金額も合わせて減少することになります。
支払う法人税等は法人の利益である所得に応じて税率も変わり、所得が多ければその分税率も高くなります。具体的には800万円が税率の分岐点となっており、評価損の計上することで税率が下がる場合には非常に大きな節税効果が期待できます。
評価損の対象となる資産
では、評価損として計上することができるものには、そのような資産が含まれているのでしょうか。評価その対象となる資産には 以下のものが含まれます
- 棚卸資産
- 有価証券
- 固定資産※
- 繰延資産
※固定資産にはソフトウェアのような無形固定資産も含まれます。
また、同じ資産であったとしても預貯金や売掛金 貸付金などの金銭債権について評価損益計上はできません。金銭債権については、別途「貸倒引当金繰入」として計上することが可能です。
評価損の税務上の取り扱い
原則として評価損は税務上の費用である「損金」 参入することはできません。仮に評価損を自由に損金参入することができるのでれば、企業としては独自の判断やタイミングで評価損を計上し、税務上の利益である「所得」を調整することができてしまうからです。
ただ例外として、評価損が損金として認められる場合があります。いくつかの条件がありますが、それらの条件を満たしている場合には損金として認められるのです。
ここでは原則として、評価損は税務上損金計上することが認められていないということを覚えておきましょう。
評価損を計上することができる一定の条件
では評価損が認められる一定の条件とはどのようなものなのでしょうか。
評価損を計上するためには、資産の「著しい損傷」、「著しい陳腐化」がキーワードとなります。棚卸資産、有価証券、固定資産、繰延資産それぞれの資産について評価損として認められる条件について具体的に解説して行きます。
棚卸資産の評価損計上条件
棚卸資産を評価損として 計上するためには
- 災害により著しく損傷したこと
- 著しく陳腐化したこと
が条件となります。
災害による著しい損傷は比較的判断がしやすいですが、著しい陳腐化についての判断はそれぞれ個人によって異なるかと思います。
国税庁では棚卸資産の著しい陳腐化について、「棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態」としています。
その具体例として、
- いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
- 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
をあげています。
これらの1や2の条件に該当している場合、またはそれに準ずる特別な事実がある場合※ には評価損として計上することができるとされています。
なお「それに準ずる特別な事実※」に該当するのは
- 破損
- 型崩れ
- 棚ざらし
- 品質変化等
などが含まれ、これらのことにより通常の方法によって販売することができないようになった場合とされています。
有価証券の評価損計上条件
では続いて、有価証券を評価損として計上するための条件を確認しましょう。有価証券が評価損として認められるためには、以下の条件を満たしている必要があります 。
- 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(企業支配株式を除く。)については、その価額が著しく低下したこと
- 1以外の有価証券及び企業支配株式に該当するものについて、その有価証券を発行する※法人の資産の状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと
1は時価が公表されている有価証券のことを指します。
「取得価格」と事業年度末の「時価」を比較して50%以上下落しており、近い将来その価格の回復が見込まれないような場合には「著しく低下している」とみなされます。
2は上場しておらず時価が公表されていない有価証券のことを指します。
それらの有価証券は時価によらなくても、精算、破産、再生、更生手続き開始の決定などにより株式の価格が著しく低下したかどうかを判断することができます。
なお、法人の資産の状態が著しく悪化した場合とは 次のようなことを指します。
- (ア)取得後相当期間を経過した後その発行法人について、特別清算開始の命令があったこと、破産手続開始の決定があったこと、再生手続開始の決定があったこと、更生手続開始の決定があったこと
- (イ)有価証券の1口又は1株当たりの現在価額が、1口又は1株当たりの従前の価額(取得時の価額)の50%以下に低下していること
また2に準ずる特別の事実があった場合にも評価損計上が認められます。
固定資産の評価損計上条件
続いて固定資産の評価損計上条件です。棚卸資産の評価損計上条件と多少異なる部分もありますので注意しましょう。
- 災害により著しく損傷したこと
- その固定資産が1年以上にわたり遊休状態にあること
- その固定資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと
- その固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと
- ※その他1から4までに準ずる特別の事実がある場合
※この特別の事実がある場合とは、具体的には次の事実をいう。
- (ア) 固定資産についてやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上使用しないため、その価額が低下したこと
- (イ) 土地を賃貸し権利金その他の一時金を収受して長期間その土地を使用させるためその土地の価額が帳簿価額を下回ったこと(その価額が50%以上低下した場合には、令第138条により損金算入ができる
棚卸資産の評価損計上条件と異なる部分は、「所在する場所の状況」も考慮されている部分となります。
固定資産に関しては持ち運びが困難なものであるため、所在する場所の状況も 鑑みる必要があり、「固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと」というものが要件に含まれています。
繰延資産の評価損計上条件
では続いて繰延資産の評価損計上条件について解説します。
- 繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出したものについては、その支出対象となった固定資産について災害、1年以上にわたる遊休、用途変更又は立地条件の変化があったこと(前述の固定資産の1から4までの場合)
- その他1に準ずる特別の事実がある場合
繰延資産には資産を賃借するための「権利金」なども含まれています。具体的には賃貸借契約時の礼金などです。
例えばこの賃貸資産が災害の被害を受け賃貸条件が変化した場合には、資産として計上している権利金部分も必要に応じて評価損を計上することができます。
またその他、例えば商店街のアーケード設置費用の負担金を繰延資産に計上していて台風で破損したような場合にも、計上していた繰延資産について評価損を計上することができます。
評価損として認められないケース
これまで評価損として認められる条件について解説してきました。ここからは評価損として認められないケースについてご紹介します。このような場合には評価損として認められませんので注意しましょう。
・棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけ
・固定資産の価額の低下が次のような事実に基づく場合
- 過度の使用又は修理の不十分等により著しく損耗していること
- 償却を行わなかったため償却不足額が生じていること
- 取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと
- 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること
これらの場合には評価損として計上することは認められません。ただし、固定資産の耐用年数の短縮が認められる場合もありますので、そちらも検討してみましょう。
評価損として 計上できる金額
評価損として計上することができる金額はその時価と帳簿価額との差額部分となります。つまり、
時価 − 帳簿価額=評価損
となります。このため、評価損として計上したい場合には資産の時価を確認する必要があり、続いて帳簿価格も把握しておく必要があります。この帳簿価額については取得価格というわけではなく、取得価額から過年度における減価償却費の合計金額(減価償却累計額)を差し引いた金額となります。時価の算出に関しては後述しますが、金額に対する客観的な根拠が必要となります。
評価損を損金参入させるための注意点
評価損は節税対策として非常に有効な方法ですが、「陳腐化」についての判断など主観的な要素が若干含まれるため税務調査では指摘されやすい項目となります。税務署から指摘を受けた際にはきちんとその金額の妥当性、評価損計上の根拠を証明できなければなりません。これからご紹介する必要資料を事前に準備しておき、税務署からの指摘を受けてもきちんと説明できるようにしておきましょう。
時価の金額の根拠
先程ご紹介したように評価損を計上するためには時価の金額を明らかにする必要があります。税務署としてはこの時価が適正であるのかも確認します。例えば帳簿価格が50万円で時価が100万円であると申告されていても、実際には時価が80万円であった場合、評価損の金額は30万円も異なってきます。
この時価の金額を設定した根拠となる資料を準備しておきましょう。例えば自社ではなく 同業の他社が類似商品について販売している場合には、それらの金額がわかる資料を用意しておくこともできます。実際にそれだけの金額まで時価が下がっているという客観的な資料を用意しておきましょう。
陳腐化の証明資料
陳腐化に関してはその証明をすることが難しい場合があります。ポイントとなるのはできるだけ客観的な証明資料を準備することです。例えば新製品が発売されている事実を証明するカタログやチラシ、実際に商品の販売実績の低下が証明できる資料、類似商品の他店での販売価格がわかる資料などを用意しておきましょう。
災害の事実と損傷の証明資料
災害による損傷により評価損を計上する場合には、災害の事実と損傷した箇所について写真を撮るなどして証明資料を用意しておきましょう。こちらの証明に関しては陳腐化などよりも証明がしやすい項目となりますが、参考資料として保管しておきましょう。
廃棄処分という選択肢も
評価損を計上することは資金の流出を伴わない節税対策であるため非常に有効です。しかし税務調査において指摘されやすい項目であることも事実です。また評価損を計上するための条件も多くあります。もし決算まである程度時間的な猶予があるのであれば、実際に廃棄処分を行い損失計上することも検討しましょう。廃棄処分を検討する議事録や廃棄したという廃棄証明書を発行してもらうなどにより、評価損よりも比較的容易に経費計上することができます。
まとめ
今回の記事では評価損による節税方法、そして損金算入が認められる条件について解説しました。評価損の最大のメリットは資金の流出を伴わない節税であること、また決算直前の節税対策としても検討できる点です。しかし容易に利益調整ができてしまうという点から税務署から指摘されやすい項目であることも事実です。これらの評価損を活用した節税対策についてご検討されている方は、専門の税理士や節税コンサルティングサービスをご利用ください。